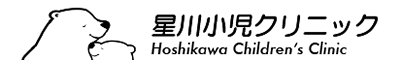星川小児クリニック: 045-336-2260
病児保育室アニモ : 045-336-2264
おねしょについて
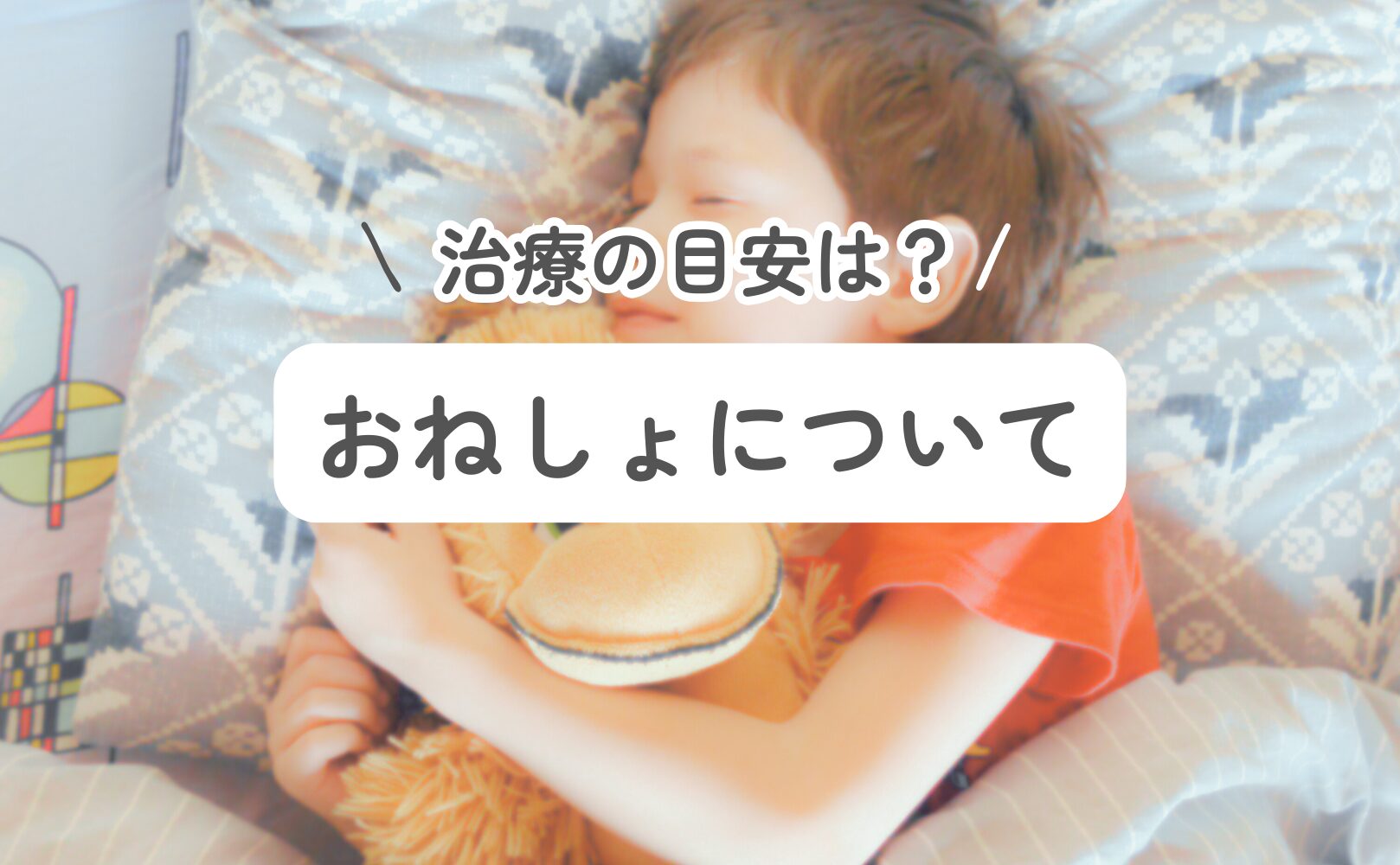
おねしょを治そう
夜尿症は、2歳のお子さんでは2人に1人、3歳では3人に1人、4歳では4人に1人、5歳では5人に1人…というように、年齢が上がるにつれて、ちょうど「1/年齢」くらいの割合で自然に減っていくことが知られています。
「そのうち治る」と言われることも多い夜尿症ですが、中には思春期や成人になっても続くケースもあります。また、お子さん自身の自信や日常生活に影響が出ることもあるため、早めに相談いただくことで、より良い結果につながることがあります。治療によって改善率が上がるという報告もあります。当院でも夜尿症のご相談や薬物療法を行っていますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。
どのくらいから治療をはじめたらいいの?
以下の表は、夜尿の頻度と年齢に応じて、どのように対応するのがよいかの目安です。
| 年齢 | 毎晩 | 週に4〜6回 | 週に2〜3回 | 週に1回以下 |
|---|---|---|---|---|
| 5歳 | ● | ● | ● | ● |
| 6〜7歳 | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 8〜9歳 | ★ | ▲ | ▲ | ● |
| 10歳以上 | ★ | ★ | ▲ | ▲ |
- ●:家庭で様子をみる
- ●:生活習慣を改善しながら家庭で様子をみる
- ▲:生活習慣を改善しても効果がなければクリニックを受診
- ★:クリニックに受診
これはあくまでも目安です。「ちょっと気になるな」と思ったら、お気軽にご相談ください。
生活習慣を見直そう
1.夜中に無理に起こさない
夜間にしっかり眠っていると、抗利尿ホルモンというホルモンが脳から多く分泌され、尿の量を減らしてくれます。無理に夜中に起こすことでこのホルモンの分泌が妨げられ、かえって夜尿症が悪化してしまう可能性があります。
2.水分は日中にしっかり、夕方以降は控えめに
夕食後は水分を控えることが基本ですが、それよりも、朝・昼・帰宅後にしっかり水分をとっておくことが大切です。喉が渇いてしまっては我慢ができないので、日中の水分補給を意識しましょう。
3.夕食は早めに
寝る直前の夕食では、夜の尿量を抑える工夫が効果を発揮しづらくなります。可能であれば、夕食は就寝の2〜3時間前までに済ませると良いでしょう。
4.塩分控えめの食事を意識する
塩分が多いと喉が渇いて、夜間の水分摂取が増えてしまいます。夕食の塩分は控えめを心がけてみてください。
5.生活リズムを整える
毎日の起床・就寝・食事の時間など、生活のリズムを安定させることも夜尿症改善の助けになります。また、便秘があると膀胱が圧迫されて夜尿につながることがあるため、排便習慣にも目を向けましょう。
6.寒さ対策をしっかりと
寒いと尿意が強くなります。冬は布団乾燥機などで寝床を暖かくし、入浴後に体をしっかり温めてから眠るようにすると効果的です。
7.就寝前のトイレを忘れずに
寝る前には必ずトイレに行く習慣をつけましょう。残尿がある場合もあるので、寝る30分前と直前の2回トイレに行くようにすると、意外と出ることもあります。
有効な薬物療法もあります
生活習慣の見直しをしても改善がみられない場合は、お薬の力を借りることも検討しましょう。第一選択薬として使われるのが「ミニリンメルト」という抗利尿ホルモン剤です。
ステロイドホルモンのイメージで心配される方もいますが、全く異なる種類のホルモン剤です。
夜間に自然に分泌されるホルモン(寝ている間はそのホルモンの働きで腎臓から膀胱に流れる水分を再吸収して尿を減らす)と同じものを、ちょっと足すというイメージです。
初診後に尿の量や濃さを測定する検査を行い、ミニリンメルトが合っているかどうかを確認した上で治療を進めていきます。
夜尿症日誌
上手にみていくには、夜間の尿量がどうかがポイントなので、日誌で記録しています。夜尿症の患者さんにお渡ししています。
モチベーションのアップにもつながるので根気よく続けていきましょう。クリニックでも日誌をお渡ししています。
以下のサイトもご参考ください
外部リンク:おねしょ・夜尿症の悩み解消「おねしょ卒業!プロジェクト」
ピスコール(アラーム療法)について
外部リンク:アワジテックのピスコール